
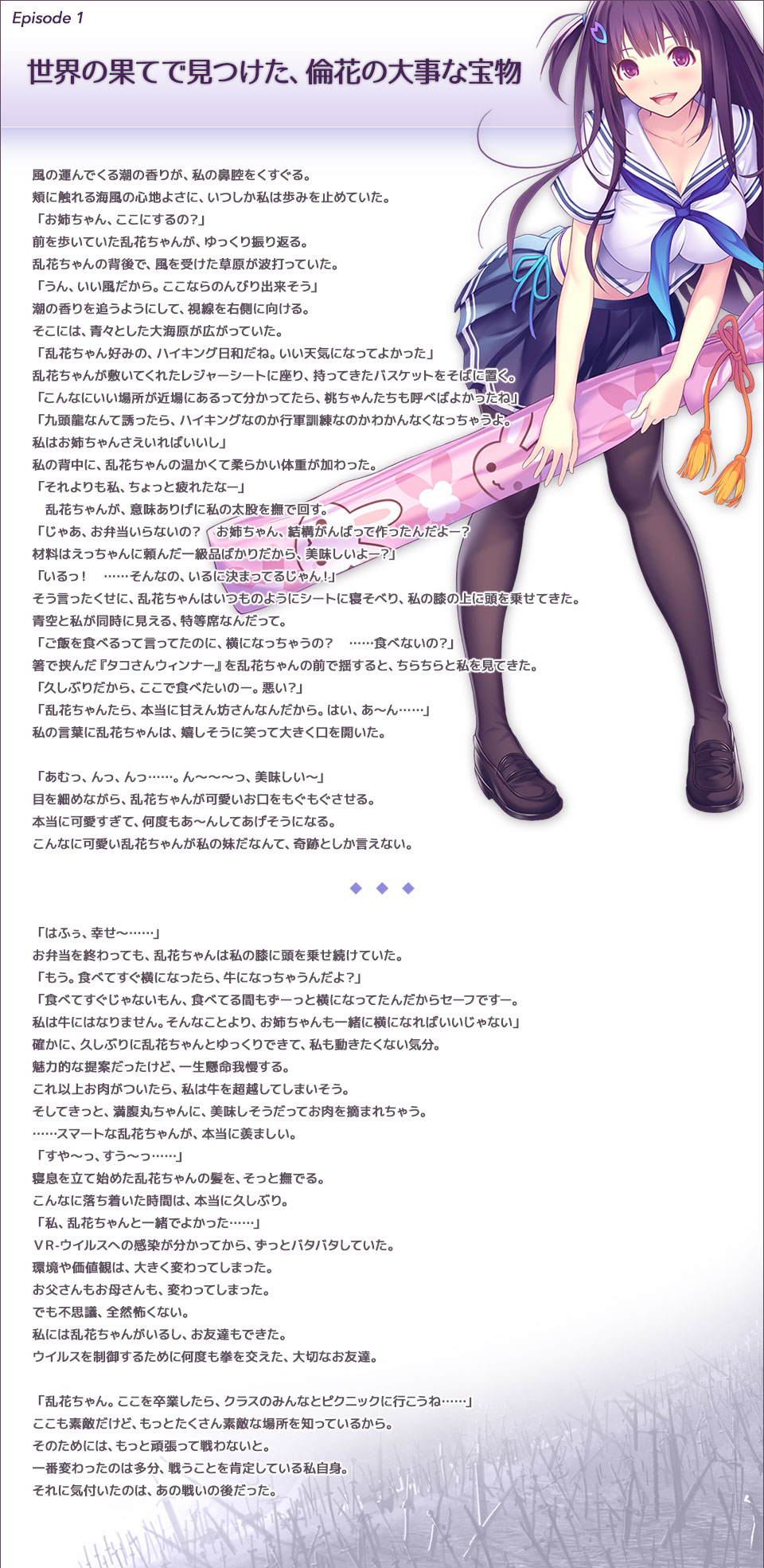
風の運んでくる潮の香りが、私の鼻腔をくすぐる。 頬に触れる海風の心地よさに、いつしか私は歩みを止めていた。 「お姉ちゃん、ここにするの?」 前を歩いていた乱花ちゃんが、ゆっくり振り返る。 乱花ちゃんの背後で、風を受けた草原が波打っていた。 「うん、いい風だから。ここならのんびり出来そう」 潮の香りを追うようにして、視線を右側に向ける。 そこには、青々とした大海原が広がっていた。 「乱花ちゃん好みの、ハイキング日和だね。いい天気になってよかった」 乱花ちゃんが敷いてくれたレジャーシートに座り、持ってきたバスケットをそばに置く。 「こんなにいい場所が近場にあるって分かってたら、桃ちゃんたちも呼べばよかったね」 「九頭龍なんて誘ったら、ハイキングなのか行軍訓練なのかわかんなくなっちゃうよ。私はお姉ちゃんさえいればいいし」 私の背中に、乱花ちゃんの温かくて柔らかい体重が加わった。 「それよりも私、ちょっと疲れたなー」 乱花ちゃんが、意味ありげに私の太股を撫で回す。 「じゃあ、お弁当いらないの? お姉ちゃん、結構がんばって作ったんだよー? 材料はえっちゃんに頼んだ一級品ばかりだから、美味しいよー?」 「いるっ! ……そんなの、いるに決まってるじゃん!」 そう言ったくせに、乱花ちゃんはいつものようにシートに寝そべり、私の膝の上に頭を乗せてきた。 青空と私が同時に見える、特等席なんだって。 「ご飯を食べるって言ってたのに、横になっちゃうの? ……食べないの?」 箸で挟んだ『タコさんウィンナー』を乱花ちゃんの前で揺すると、ちらちらと私を見てきた。 「久しぶりだから、ここで食べたいのー。悪い?」 「乱花ちゃんたら、本当に甘えん坊さんなんだから。はい、あ〜ん……」 私の言葉に乱花ちゃんは、嬉しそうに笑って大きく口を開いた。 「あむっ、んっ、んっ……。ん〜〜〜っ、美味しい〜」 目を細めながら、乱花ちゃんが可愛いお口をもぐもぐさせる。 本当に可愛すぎて、何度もあ〜んしてあげそうになる。 こんなに可愛い乱花ちゃんが私の妹だなんて、奇跡としか言えない。 ◆ ◆ ◆ 「はふぅ、幸せ〜……」 お弁当を終わっても、乱花ちゃんは私の膝に頭を乗せ続けていた。 「もう。食べてすぐ横になったら、牛になっちゃうんだよ?」 「食べてすぐじゃないもん、食べてる間もずーっと横になってたんだからセーフですー。私は牛にはなりません。そんなことより、お姉ちゃんも一緒に横になればいいじゃない」 確かに、久しぶりに乱花ちゃんとゆっくりできて、私も動きたくない気分。 魅力的な提案だったけど、一生懸命我慢する。 これ以上お肉がついたら、私は牛を超越してしまいそう。 そしてきっと、満腹丸ちゃんに、美味しそうだってお肉を摘まれちゃう。 ……スマートな乱花ちゃんが、本当に羨ましい。 「すや〜っ、すう〜っ……」 寝息を立て始めた乱花ちゃんの髪を、そっと撫でる。 こんなに落ち着いた時間は、本当に久しぶり。 「私、乱花ちゃんと一緒でよかった……」 VR-ウイルスへの感染が分かってから、ずっとバタバタしていた。 環境や価値観は、大きく変わってしまった。 お父さんもお母さんも、変わってしまった。 でも不思議、全然怖くない。 私には乱花ちゃんがいるし、お友達もできた。 ウイルスを制御するために何度も拳を交えた、大切なお友達。 「乱花ちゃん。ここを卒業したら、クラスのみんなとピクニックに行こうね……」 ここも素敵だけど、もっとたくさん素敵な場所を知っているから。 そのためには、もっと頑張って戦わないと。 一番変わったのは多分、戦うことを肯定している私自身。 それに気付いたのは、あの戦いの後だった。
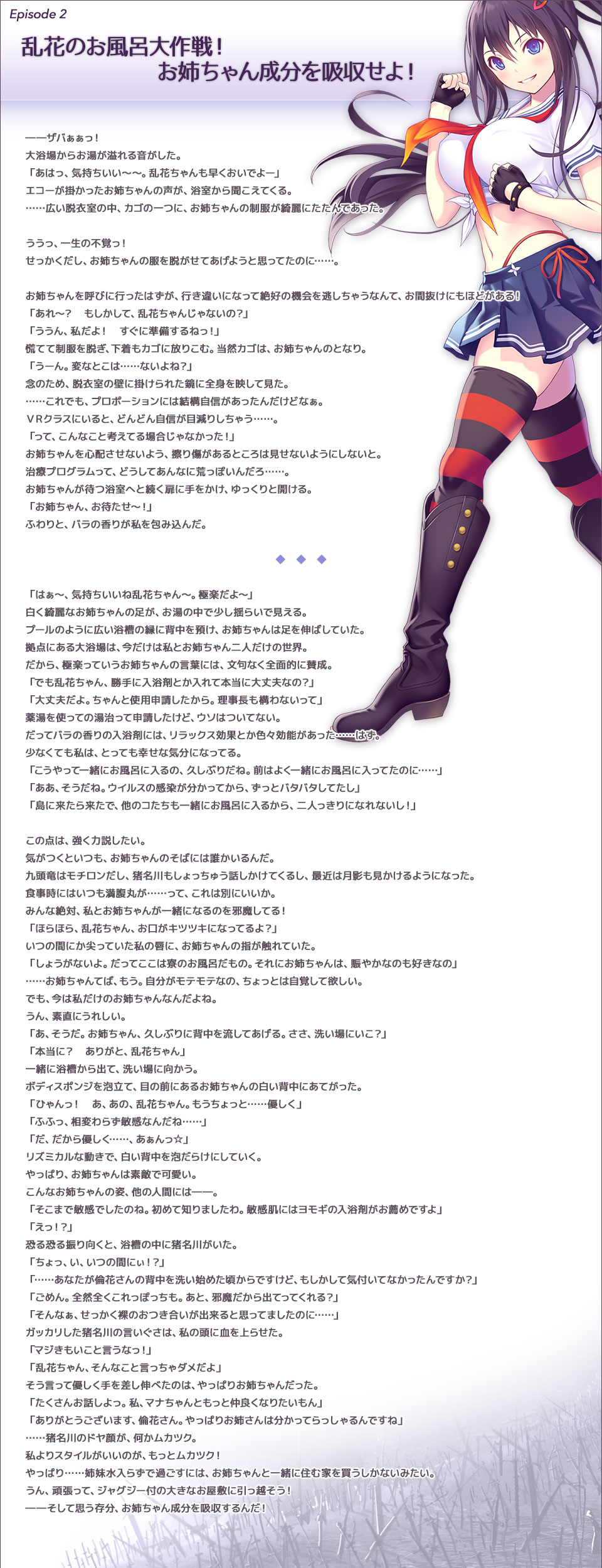
――ザバぁぁっ! 大浴場からお湯が溢れる音がした。 「あはっ、気持ちいい〜〜。乱花ちゃんも早くおいでよー」 エコーが掛かったお姉ちゃんの声が、浴室から聞こえてくる。 ……広い脱衣室の中、カゴの一つに、お姉ちゃんの制服が綺麗にたたんであった。 ううっ、一生の不覚っ! せっかくだし、お姉ちゃんの服を脱がせてあげようと思ってたのに……。 お姉ちゃんを呼びに行ったはずが、行き違いになって絶好の機会を逃しちゃうなんて、お間抜けにもほどがある! 「あれ〜? もしかして、乱花ちゃんじゃないの?」 「ううん、私だよ! すぐに準備するねっ!」 慌てて制服を脱ぎ、下着もカゴに放りこむ。当然カゴは、お姉ちゃんのとなり。 「うーん。変なとこは……ないよね?」 念のため、脱衣室の壁に掛けられた鏡に全身を映して見た。 ……これでも、プロポーションには結構自信があったんだけどなぁ。 VRクラスにいると、どんどん自信が目減りしちゃう……。 「って、こんなこと考えてる場合じゃなかった!」 お姉ちゃんを心配させないよう、擦り傷があるところは見せないようにしないと。 治療プログラムって、どうしてあんなに荒っぽいんだろ……。 お姉ちゃんが待つ浴室へと続く扉に手をかけ、ゆっくりと開ける。 「お姉ちゃん、お待たせ〜!」 ふわりと、バラの香りが私を包み込んだ。 ◆ ◆ ◆ 「はぁ〜、気持ちいいね乱花ちゃん〜。極楽だよ〜」 白く綺麗なお姉ちゃんの足が、お湯の中で少し揺らいで見える。 プールのように広い浴槽の縁に背中を預け、お姉ちゃんは足を伸ばしていた。 拠点にある大浴場は、今だけは私とお姉ちゃん二人だけの世界。 だから、極楽っていうお姉ちゃんの言葉には、文句なく全面的に賛成。 「でも乱花ちゃん、勝手に入浴剤とか入れて本当に大丈夫なの?」 「大丈夫だよ。ちゃんと使用申請したから。理事長も構わないって」 薬湯を使っての湯治って申請したけど、ウソはついてない。 だってバラの香りの入浴剤には、リラックス効果とか色々効能があった……はず。 少なくても私は、とっても幸せな気分になってる。 「こうやって一緒にお風呂に入るの、久しぶりだね。前はよく一緒にお風呂に入ってたのに……」 「ああ、そうだね。ウイルスの感染が分かってから、ずっとバタバタしてたし」 「島に来たら来たで、他のコたちも一緒にお風呂に入るから、二人っきりになれないし!」 この点は、強く力説したい。 気がつくといつも、お姉ちゃんのそばには誰かいるんだ。 九頭竜はモチロンだし、猪名川もしょっちゅう話しかけてくるし、最近は月影も見かけるようになった。 食事時にはいつも満腹丸が……って、これは別にいいか。 みんな絶対、私とお姉ちゃんが一緒になるのを邪魔してる! 「ほらほら、乱花ちゃん、お口がキツツキになってるよ?」 いつの間にか尖っていた私の唇に、お姉ちゃんの指が触れていた。 「しょうがないよ。だってここは寮のお風呂だもの。それにお姉ちゃんは、賑やかなのも好きなの」 ……お姉ちゃんてば、もう。自分がモテモテなの、ちょっとは自覚して欲しい。 でも、今は私だけのお姉ちゃんなんだよね。 うん、素直にうれしい。 「あ、そうだ。お姉ちゃん、久しぶりに背中を流してあげる。ささ、洗い場にいこ?」 「本当に? ありがと、乱花ちゃん」 一緒に浴槽から出て、洗い場に向かう。 ボディスポンジを泡立て、目の前にあるお姉ちゃんの白い背中にあてがった。 「ひゃんっ! あ、あの、乱花ちゃん。もうちょっと……優しく」 「ふふっ、相変わらず敏感なんだね……」 「だ、だから優しく……、あぁんっ☆」 リズミカルな動きで、白い背中を泡だらけにしていく。 やっぱり、お姉ちゃんは素敵で可愛い。 こんなお姉ちゃんの姿、他の人間には――。 「そこまで敏感でしたのね。初めて知りましたわ。敏感肌にはヨモギの入浴剤がお薦めですよ」 「えっ!?」 恐る恐る振り向くと、浴槽の中に猪名川がいた。 「ちょっ、い、いつの間にぃ!?」 「……あなたが倫花さんの背中を洗い始めた頃からですけど、もしかして気付いてなかったんですか?」 「ごめん。全然全くこれっぽっちも。あと、邪魔だから出てってくれる?」 「そんなぁ、せっかく裸のおつき合いが出来ると思ってましたのに……」 ガッカリした猪名川の言いぐさは、私の頭に血を上らせた。 「マジきもいこと言うなっ!」 「乱花ちゃん、そんなこと言っちゃダメだよ」 そう言って優しく手を差し伸べたのは、やっぱりお姉ちゃんだった。 「たくさんお話しよっ。私、マナちゃんともっと仲良くなりたいもん」 「ありがとうございます、倫花さん。やっぱりお姉さんは分かってらっしゃるんですね」 ……猪名川のドヤ顔が、何かムカツク。 私よりスタイルがいいのが、もっとムカツク! やっぱり……姉妹水入らずで過ごすには、お姉ちゃんと一緒に住む家を買うしかないみたい。 うん、頑張って、ジャグジー付の大きなお屋敷に引っ越そう! ――そして思う存分、お姉ちゃん成分を吸収するんだ!
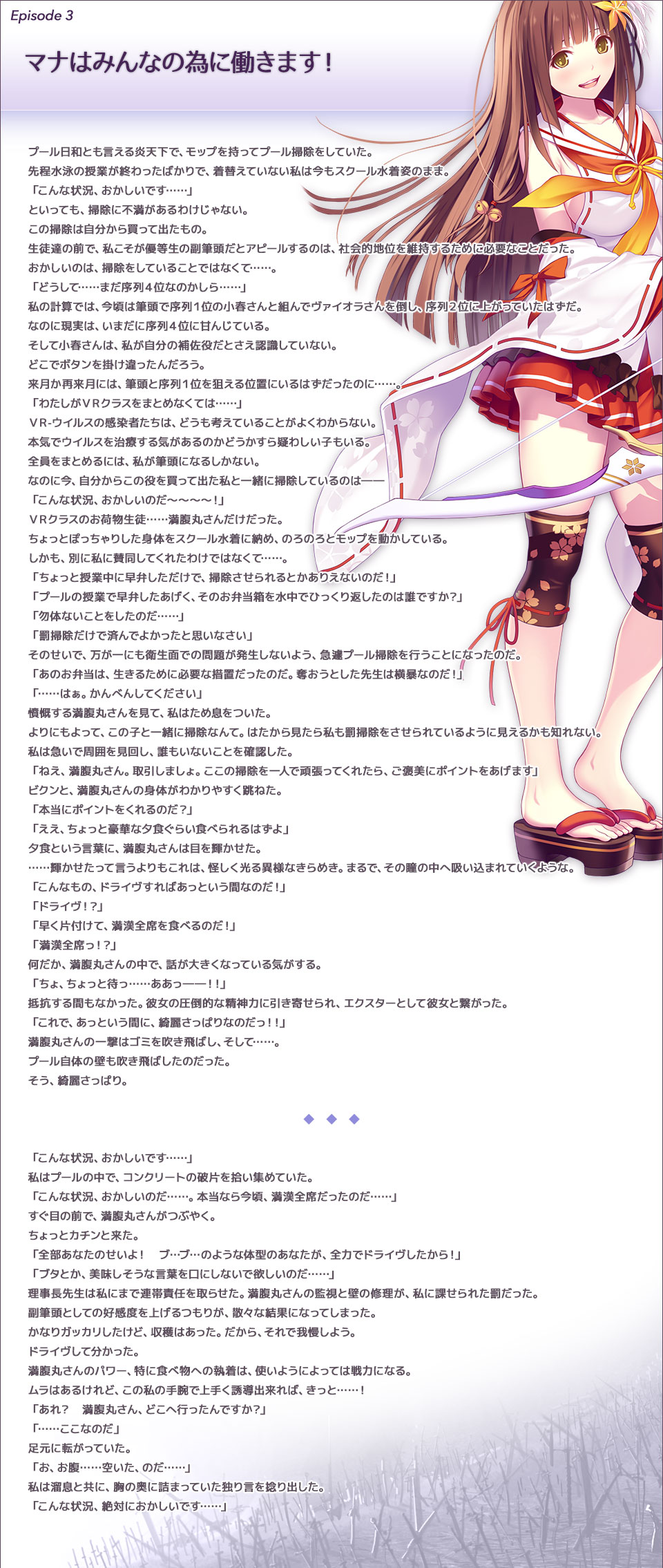
プール日和とも言える炎天下で、モップを持ってプール掃除をしていた。 先程水泳の授業が終わったばかりで、着替えていない私は今もスクール水着姿のまま。 「こんな状況、おかしいです……」 といっても、掃除に不満があるわけじゃない。 この掃除は自分から買って出たもの。 生徒達の前で、私こそが優等生の副筆頭だとアピールするのは、社会的地位を維持するために必要なことだった。 おかしいのは、掃除をしていることではなくて……。 「どうして……まだ序列4位なのかしら……」 私の計算では、今頃は筆頭で序列1位の小春さんと組んでヴァイオラさんを倒し、序列2位に上がっていたはずだ。 なのに現実は、いまだに序列4位に甘んじている。 そして小春さんは、私が自分の補佐役だとさえ認識していない。 どこでボタンを掛け違ったんだろう。 来月か再来月には、筆頭と序列1位を狙える位置にいるはずだったのに……。 「わたしがVRクラスをまとめなくては……」 VR-ウイルスの感染者たちは、どうも考えていることがよくわからない。 本気でウイルスを治療する気があるのかどうかすら疑わしい子もいる。 全員をまとめるには、私が筆頭になるしかない。 なのに今、自分からこの役を買って出た私と一緒に掃除しているのは―― 「こんな状況、おかしいのだ〜〜〜〜!」 VRクラスのお荷物生徒……満腹丸さんだけだった。 ちょっとぽっちゃりした身体をスクール水着に納め、のろのろとモップを動かしている。 しかも、別に私に賛同してくれたわけではなくて……。 「ちょっと授業中に早弁しただけで、掃除させられるとかありえないのだ!」 「プールの授業で早弁したあげく、そのお弁当箱を水中でひっくり返したのは誰ですか?」 「勿体ないことをしたのだ……」 「罰掃除だけで済んでよかったと思いなさい」 そのせいで、万が一にも衛生面での問題が発生しないよう、急遽プール掃除を行うことになったのだ。 「あのお弁当は、生きるために必要な措置だったのだ。奪おうとした先生は横暴なのだ!」 「……はぁ。かんべんしてください」 憤慨する満腹丸さんを見て、私はため息をついた。 よりにもよって、この子と一緒に掃除なんて。はたから見たら私も罰掃除をさせられているように見えるかも知れない。 私は急いで周囲を見回し、誰もいないことを確認した。 「ねえ、満腹丸さん。取引しましょ。ここの掃除を一人で頑張ってくれたら、ご褒美にポイントをあげます」 ビクンと、満腹丸さんの身体がわかりやすく跳ねた。 「本当にポイントをくれるのだ?」 「ええ、ちょっと豪華な夕食ぐらい食べられるはずよ」 夕食という言葉に、満腹丸さんは目を輝かせた。 ……輝かせたって言うよりもこれは、怪しく光る異様なきらめき。まるで、その瞳の中へ吸い込まれていくような。 「こんなもの、ドライヴすればあっという間なのだ!」 「ドライヴ!?」 「早く片付けて、満漢全席を食べるのだ!」 「満漢全席っ!?」 何だか、満腹丸さんの中で、話が大きくなっている気がする。 「ちょ、ちょっと待っ……ああっ――!!」 抵抗する間もなかった。彼女の圧倒的な精神力に引き寄せられ、エクスターとして彼女と繋がった。 「これで、あっという間に、綺麗さっぱりなのだっ!!」 満腹丸さんの一撃はゴミを吹き飛ばし、そして……。 プール自体の壁も吹き飛ばしたのだった。 そう、綺麗さっぱり。 ◆ ◆ ◆ 「こんな状況、おかしいです……」 私はプールの中で、コンクリートの破片を拾い集めていた。 「こんな状況、おかしいのだ……。本当なら今頃、満漢全席だったのだ……」 すぐ目の前で、満腹丸さんがつぶやく。 ちょっとカチンと来た。 「全部あなたのせいよ! ブ…ブ…のような体型のあなたが、全力でドライヴしたから!」 「ブタとか、美味しそうな言葉を口にしないで欲しいのだ……」 理事長先生は私にまで連帯責任を取らせた。満腹丸さんの監視と壁の修理が、私に課せられた罰だった。 副筆頭としての好感度を上げるつもりが、散々な結果になってしまった。 かなりガッカリしたけど、収穫はあった。だから、それで我慢しよう。 ドライヴして分かった。 満腹丸さんのパワー、特に食べ物への執着は、使いようによっては戦力になる。 ムラはあるけれど、この私の手腕で上手く誘導出来れば、きっと……! 「あれ? 満腹丸さん、どこへ行ったんですか?」 「……ここなのだ」 足元に転がっていた。 「お、お腹……空いた、のだ……」 私は溜息と共に、胸の奥に詰まっていた独り言を捻り出した。 「こんな状況、絶対におかしいです……」

「月影さんっ、あ、あの、よろしいでしょうかっ!」 放課後、一般居住区を巡回していた私は、一般クラスの生徒たちに声をかけられた。 今までのパターンだと、半数がスイーツへのお誘いで、もう半数は……。 「お願いがありますっ。私たちに稽古をつけてくださいっ」 今回は、定期戦前の自主訓練の方だったようだ。 見たところ、全員で10名ほど。序列上位のパートナーが何組か見える。 リブレイターとエクスターはちゃんと数を揃えてきたらしい。 「稽古は……ドライヴしての模擬戦でいいですね?」 「は、はいっ! ありがとうございます!」 パッと、彼女たちの表情が明るくなる。 最初からドライヴした私と戦うつもりだったんでしょう――とは言わない。 他の生徒たちへの指導も、筆頭の大事な役目。 「では、正式な模擬戦ルールで戦いましょう。それでいいですか、マナさん?」 「私はただの人数合わせです。VRクラスの生徒は色々便利だと思って」 一般クラスの生徒の中に混じっていたマナさんが、微笑みを浮かべている。 恐らく、この模擬戦の主催者はマナさんだろう。 私に何かアピールしたくて、この戦いを計画したに違いない。 そういう、自分を高めようとする努力は嫌いじゃない。 それは誰よりも私が望んでいることなのだから。 「時間が勿体ないですね。空き地に移動して、戦いを始めましょう」 居住区の治安パトロールも重要な任務だけど、この学園でもっとも優先すべきは、戦うこと。戦い、自分を高めることで、己の中のV-ウイルスを制御する。戦いこそが、未来に続く道をつくる。 私が筆頭である以上、生徒達が戦いを求めるなら、選択はただ一つだった。 「戦いは2戦。私はリブレイターとエクスターを、それぞれ1回務めます」 「それでは、小春さんのパートナーは副筆頭の私が……」 「いえ、マナさんは一般クラスの皆さんに加わってください。彼女たちのフォローを」 「ええっ? そんな、それじゃ私の計画が……」 「お願いできますか?」 「……はい」 マナさんは目に見えてがっくりしている。 ごめんなさいね。 「ルールは単純です。私が臨時パートナーとドライヴし、臨時指導員になります。 残り全員でかかってきてください」 「え。本当に全員で行ってもいいんですか?」 先ほどまで肩を落としていたマナさんの目が、ギラリと輝くのが見えた。 有意義な訓練になりそうだ。 ◆ ◆ ◆ 前言撤回。 戦いは、とても不本意なものになってしまった。 戦いは全て私の勝利。でも内容は反省すべき点がいくつもあった。 やはり私が本気を出すためには、波長があうパートナーが必要らしい。 「うぐっ……や、やっぱりVR-ウイルス感染者同士じゃないとダメですよね! ね!」 2戦とも真っ先に敗北しているのに、マナさんが妙に晴れ晴れした表情で言った。 やはり彼女も同じ結論にたどり着いているみたいだ。 「というわけで小春さん、次は私と組んでください! VRクラスの真の実力を見せましょう! ……なぁんて」 「いえ、遠慮します。1回ずつと最初に言いましたから」 「そ、そんなぁ……。私は何のためにこんな苦労を……」 機会は誰にも平等に。 そうあるべきだと私は思っている。 「マナさん。今回の模擬戦の取りまとめ、ご苦労様でした。次の授業で組みましょう」 後の始末と生徒たちの誘導をマナさんに任せ、私はパトロールに戻った。 V-ウイルスに勝つには、己が完璧であるだけでは足りない。 ドライヴを重ねれば重ねるほど、パートナーがいてこそだと強く感じていた。 あまり治療プログラムには参加していなかった私だけれど、これからはなるべく参加するように心がけよう。 彼女たちの中に私と互いを高めあえる人間がいるか、確かめる方法を考えなければ。 「そろそろ、次の段階に進んでも構わない時期ですよね」 私が誰よりも強い理由。 よく聞かれるけれど、それはとても簡単なことだった。 次こそは、先生に勝ちたい。勝って自分の限界を超えてみたい……。 超えた先のことはまだ想像すらできないけれど、そこへ思いを馳せるとき、私の胸は微かに高鳴る。 だから私は戦い続ける。 限界の、その一歩先へ進むために。
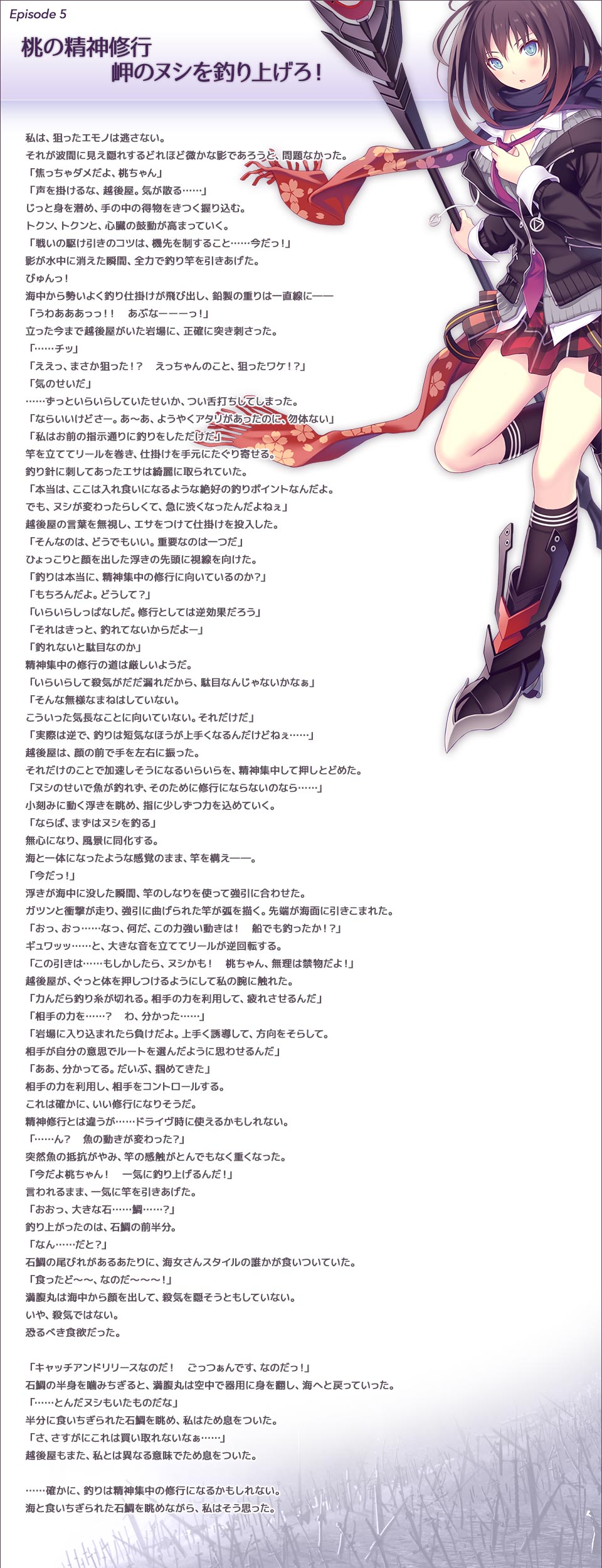
私は、狙ったエモノは逃さない。 それが波間に見え隠れするどれほど微かな影であろうと、問題なかった。 「焦っちゃダメだよ、桃ちゃん」 「声を掛けるな、越後屋。気が散る……」 じっと身を潜め、手の中の得物をきつく握り込む。 トクン、トクンと、心臓の鼓動が高まっていく。 「戦いの駆け引きのコツは、機先を制すること……今だっ!」 影が水中に消えた瞬間、全力で釣り竿を引きあげた。 びゅんっ! 海中から勢いよく釣り仕掛けが飛び出し、鉛製の重りは一直線に―― 「うわあああっっ!! あぶなーーーっ!」 立った今まで越後屋がいた岩場に、正確に突き刺さった。 「……チッ」 「ええっ、まさか狙った!? えっちゃんのこと、狙ったワケ!?」 「気のせいだ」 ……ずっといらいらしていたせいか、つい舌打ちしてしまった。 「ならいいけどさー。あ〜あ、ようやくアタリがあったのに、勿体ない」 「私はお前の指示通りに釣りをしただけだ」 竿を立ててリールを巻き、仕掛けを手元にたぐり寄せる。 釣り針に刺してあったエサは綺麗に取られていた。 「本当は、ここは入れ食いになるような絶好の釣りポイントなんだよ。 でも、ヌシが変わったらしくて、急に渋くなったんだよねぇ」 越後屋の言葉を無視し、エサをつけて仕掛けを投入した。 「そんなのは、どうでもいい。重要なのは一つだ」 ひょっこりと顔を出した浮きの先頭に視線を向けた。 「釣りは本当に、精神集中の修行に向いているのか?」 「もちろんだよ。どうして?」 「いらいらしっぱなしだ。修行としては逆効果だろう」 「それはきっと、釣れてないからだよー」 「釣れないと駄目なのか」 精神集中の修行の道は厳しいようだ。 「いらいらして殺気がだだ漏れだから、駄目なんじゃないかなぁ」 「そんな無様なまねはしていない。 こういった気長なことに向いていない。それだけだ」 「実際は逆で、釣りは短気なほうが上手くなるんだけどねぇ……」 越後屋は、顔の前で手を左右に振った。 それだけのことで加速しそうになるいらいらを、精神集中して押しとどめた。 「ヌシのせいで魚が釣れず、そのために修行にならないのなら……」 小刻みに動く浮きを眺め、指に少しずつ力を込めていく。 「ならば、まずはヌシを釣る」 無心になり、風景に同化する。 海と一体になったような感覚のまま、竿を構え――。 「今だっ!」 浮きが海中に没した瞬間、竿のしなりを使って強引に合わせた。 ガツンと衝撃が走り、強引に曲げられた竿が弧を描く。先端が海面に引きこまれた。 「おっ、おっ……なっ、何だ、この力強い動きは! 船でも釣ったか!?」 ギュワッッ……と、大きな音を立ててリールが逆回転する。 「この引きは……もしかしたら、ヌシかも! 桃ちゃん、無理は禁物だよ!」 越後屋が、ぐっと体を押しつけるようにして私の腕に触れた。 「力んだら釣り糸が切れる。相手の力を利用して、疲れさせるんだ」 「相手の力を……? わ、分かった……」 「岩場に入り込まれたら負けだよ。上手く誘導して、方向をそらして。 相手が自分の意思でルートを選んだように思わせるんだ」 「ああ、分かってる。だいぶ、掴めてきた」 相手の力を利用し、相手をコントロールする。 これは確かに、いい修行になりそうだ。 精神修行とは違うが……ドライヴ時に使えるかもしれない。 「……ん? 魚の動きが変わった?」 突然魚の抵抗がやみ、竿の感触がとんでもなく重くなった。 「今だよ桃ちゃん! 一気に釣り上げるんだ!」 言われるまま、一気に竿を引きあげた。 「おおっ、大きな石……鯛……?」 釣り上がったのは、石鯛の前半分。 「なん……だと?」 石鯛の尾びれがあるあたりに、海女さんスタイルの誰かが食いついていた。 「食ったど〜〜、なのだ〜〜〜!」 満腹丸は海中から顔を出して、殺気を隠そうともしていない。 いや、殺気ではない。 恐るべき食欲だった。 「キャッチアンドリリースなのだ! ごっつぁんです、なのだっ!」 石鯛の半身を噛みちぎると、満腹丸は空中で器用に身を翻し、海へと戻っていった。 「……とんだヌシもいたものだな」 半分に食いちぎられた石鯛を眺め、私はため息をついた。 「さ、さすがにこれは買い取れないなぁ……」 越後屋もまた、私とは異なる意味でため息をついた。 ……確かに、釣りは精神集中の修行になるかもしれない。 海と食いちぎられた石鯛を眺めながら、私はそう思った。

「やったー! これは味の宝石箱なのだ〜!」 テーブルの上一面に並べられた料理から、極上の匂いが、美味しそうな匂いがする! 「ふぁ〜、この匂いだけで、ご飯が三合は食べられるのだ……」 お口の中がトロトロなのだ。 もちろん、ご飯三合の他にチャーハンも天津飯も頼んであるのだ。 「チキンソテーに、回鍋肉に、ピザ・マルゲリータ! これも全部食べていいの? むーんちゃん?」 「また、その呼び方ですか。月影でも小春でもなく……」 テーブルの反対側に座るむーんちゃんは、困ったように首を傾げた。 「あなたが頼んだものですから、お好きにどうぞ」 「ありがとうなのだ、女神様!」 「それもやめてください……」 そう言われても、女神様としか言いようがないのだ。 「じゃあ、天使様なのだ! 腹ぺこで倒れてた満腹丸ちゃんを、このパライソに連れてきてくれましたし?」 それに、手持ちがない満腹丸ちゃんに、気にせず注文していいって言ってくれたのだ。 「だから、やめてください。筆頭としての義務を果たしただけです」 お礼に何かおごれと言わなかったのだ。いい人なのだ。 「それじゃ遠慮なく、いただきますなのだ!」 スプーンとフォークを両手にすちゃっと装備して、ごちそうを大きくすくい取ったら、次の瞬間には頬ばってた。 口の中に広がったのは、焼き色がついた鶏皮の「ぱりっ」と、脂に満ちた肉の「ぷりっ」。香ばしい匂いが鼻から抜ける。 お腹がぐるぐると高速回転し、ご飯がいくらでも流れ込む感じ。 胃袋と同時に、心が満たされていくのだー。 「美味ひー、美味ひーのだー!」 ここは本当にいいところなのだ。 だって、ポイントさえあれば、美味しいご飯が食べ放題。 運動して、戦って、お腹を空かせて。 お腹いっぱい美味しいご飯を食べる。 そしてまた戦って、お腹を空かせて。 「最高すぎるのだ! 天国なのだ!」 ここの生活が窮屈だって人もいるみたいだけど、何が不満なんだろー? 「天国、ですか?」 「そうなのだ。だって、安全に過ごせて美味しいご飯が食べられるわけですし?」 「それが、満腹丸ちゃんさんにとっての天国の定義なんですね」 今度はピザを頬ばって、モッツァレラチーズの味わいと伸びを堪能する。 う〜〜〜〜ん、デリィーーシャス! なのだ! やっぱりここは天国! 決定なのだ! 「むーんちゃんの天国は、それと違うのだ?」 「そうですね。私は、頑張ったことや努力したことに報いてくれる場所のことだと思っています」 「なんか、大変そうなのだ……。天国のように甘くなさそうなのだ」 「それは、ここも同じですよ?」 むーんちゃんは立ち上がり、満腹丸ちゃんの前にレシートを差し出した。 「これは、なんなのだ?」 「今回立て替えた食費分のポイントです。これは次回の収入から天引きしておきますね」 「……え? え? 意味がわからないのだ……。だって……これ……むーんちゃんが、気にせず注文していいって……言って……」 レシートを持つ手が、プルプルと震えた。 「はい、言いましたよ。だって、今は私が立て替えますけど、最終的に支払うのは満腹丸ちゃんさんですから」 むーんちゃんは、満腹丸ちゃんの顔を見て、不思議そうに首を傾げた。 「お、おごりだと思って、好き勝手頼んでしまったのだ……」 「あなたの天国は、普通の学園以上に、自己管理を求められるのです。では、ごきげんよう」 それだけ言い残し、むーんちゃんはどこかに消えてしまった……。 「そ、そんなぁ……」 レシートに並んだ数字に、目の前が暗くなる。 ぽ、ポイントさえあれば、美味しいご飯が食べ放題。 ここは、とっても世知辛い天国なのだ……。
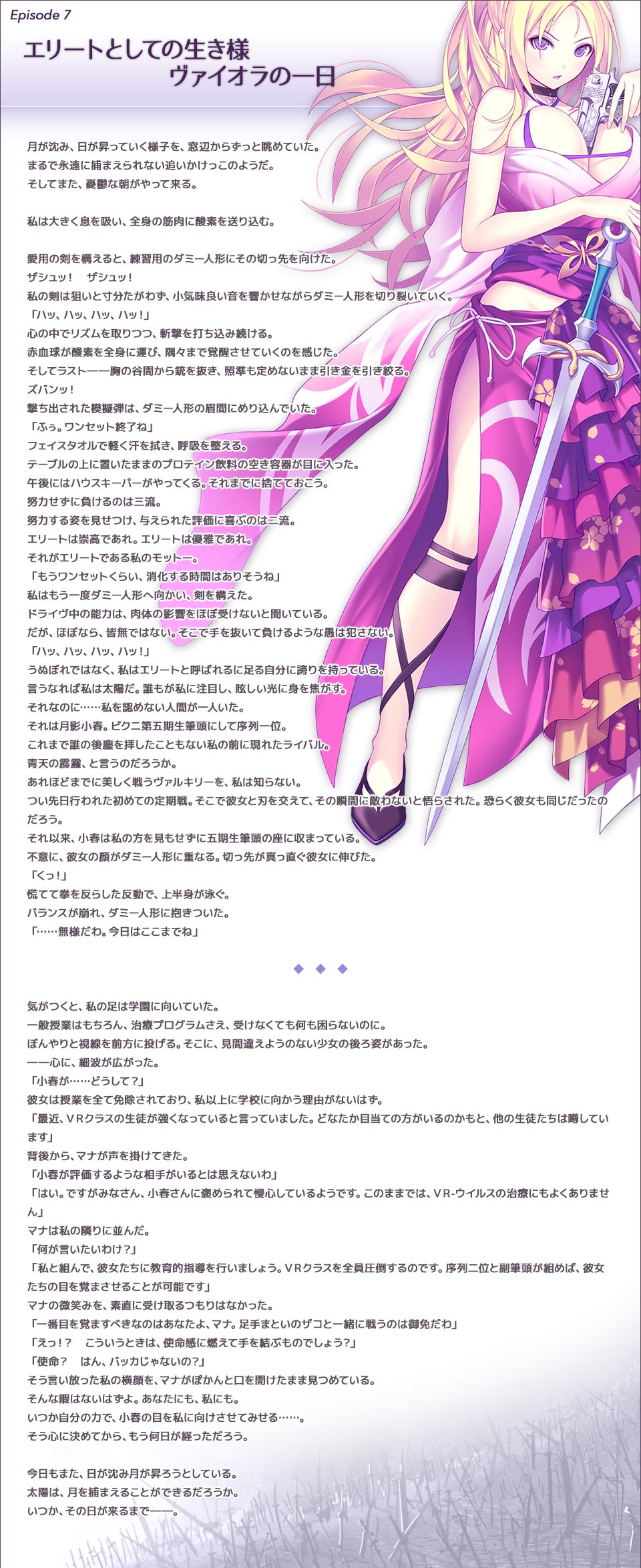
月が沈み、日が昇っていく様子を、窓辺からずっと眺めていた。 まるで永遠に捕まえられない追いかけっこのようだ。 そしてまた、憂鬱な朝がやって来る。 私は大きく息を吸い、全身の筋肉に酸素を送り込む。 愛用の剣を構えると、練習用のダミー人形にその切っ先を向けた。 ザシュッ! ザシュッ! 私の剣は狙いと寸分たがわず、小気味良い音を響かせながらダミー人形を切り裂いていく。 「ハッ、ハッ、ハッ、ハッ!」 心の中でリズムを取りつつ、斬撃を打ち込み続ける。 赤血球が酸素を全身に運び、隅々まで覚醒させていくのを感じた。 そしてラスト――胸の谷間から銃を抜き、照準も定めないまま引き金を引き絞る。 ズバンッ! 撃ち出された模擬弾は、ダミー人形の眉間にめり込んでいた。 「ふぅ。ワンセット終了ね」 フェイスタオルで軽く汗を拭き、呼吸を整える。 テーブルの上に置いたままのプロテイン飲料の空き容器が目に入った。 午後にはハウスキーパーがやってくる。それまでに捨てておこう。 努力せずに負けるのは三流。 努力する姿を見せつけ、与えられた評価に喜ぶのは二流。 エリートは崇高であれ。エリートは優雅であれ。 それがエリートである私のモットー。 「もうワンセットくらい、消化する時間はありそうね」 私はもう一度ダミー人形へ向かい、剣を構えた。 ドライヴ中の能力は、肉体の影響をほぼ受けないと聞いている。 だが、ほぼなら、皆無ではない。そこで手を抜いて負けるような愚は犯さない。 「ハッ、ハッ、ハッ、ハッ!」 うぬぼれではなく、私はエリートと呼ばれるに足る自分に誇りを持っている。 言うなれば私は太陽だ。誰もが私に注目し、眩しい光に身を焦がす。 それなのに……私を認めない人間が一人いた。 それは月影小春。ビクニ第五期生筆頭にして序列一位。 これまで誰の後塵を拝したこともない私の前に現れたライバル。 青天の霹靂、と言うのだろうか。 あれほどまでに美しく戦うヴァルキリーを、私は知らない。 つい先日行われた初めての定期戦。そこで彼女と刃を交えて、その瞬間に敵わないと悟らされた。恐らく彼女も同じだったのだろう。 それ以来、小春は私の方を見もせずに五期生筆頭の座に収まっている。 不意に、彼女の顔がダミー人形に重なる。切っ先が真っ直ぐ彼女に伸びた。 「くっ!」 慌てて拳を反らした反動で、上半身が泳ぐ。 バランスが崩れ、ダミー人形に抱きついた。 「……無様だわ。今日はここまでね」 ◆ ◆ ◆ 気がつくと、私の足は学園に向いていた。 一般授業はもちろん、治療プログラムさえ、受けなくても何も困らないのに。 ぼんやりと視線を前方に投げる。そこに、見間違えようのない少女の後ろ姿があった。 ――心に、細波が広がった。 「小春が……どうして?」 彼女は授業を全て免除されており、私以上に学校に向かう理由がないはず。 「最近、VRクラスの生徒が強くなっていると言っていました。どなたか目当ての方がいるのかもと、他の生徒たちは噂しています」 背後から、マナが声を掛けてきた。 「小春が評価するような相手がいるとは思えないわ」 「はい。ですがみなさん、小春さんに褒められて慢心しているようです。このままでは、VR-ウイルスの治療にもよくありません」 マナは私の隣りに並んだ。 「何が言いたいわけ?」 「私と組んで、彼女たちに教育的指導を行いましょう。VRクラスを全員圧倒するのです。序列二位と副筆頭が組めば、彼女たちの目を覚まさせることが可能です」 マナの微笑みを、素直に受け取るつもりはなかった。 「一番目を覚ますべきなのはあなたよ、マナ。足手まといのザコと一緒に戦うのは御免だわ」 「えっ!? こういうときは、使命感に燃えて手を結ぶものでしょう?」 「使命? はん、バッカじゃないの?」 そう言い放った私の横顔を、マナがぽかんと口を開けたまま見つめている。 そんな暇はないはずよ。あなたにも、私にも。 いつか自分の力で、小春の目を私に向けさせてみせる……。 そう心に決めてから、もう何日が経っただろう。 今日もまた、日が沈み月が昇ろうとしている。 太陽は、月を捕まえることができるだろうか。 いつか、その日が来るまで――。
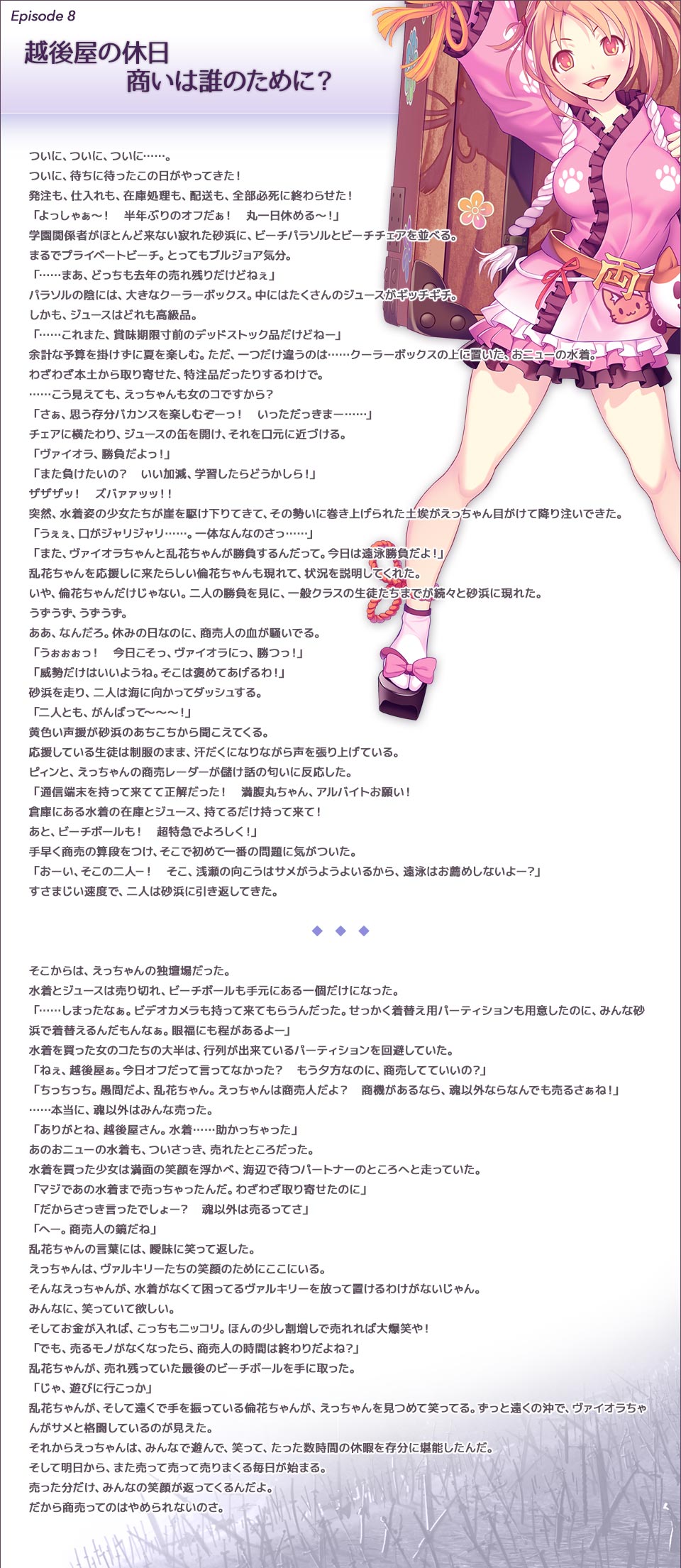
ついに、ついに、ついに……。 ついに、待ちに待ったこの日がやってきた! 発注も、仕入れも、在庫処理も、配送も、全部必死に終わらせた! 「よっしゃぁ〜! 半年ぶりのオフだぁ! 丸一日休める〜!」 学園関係者がほとんど来ない寂れた砂浜に、ビーチパラソルとビーチチェアを並べる。 まるでプライベートビーチ。とってもブルジョア気分。 「……まあ、どっちも去年の売れ残りだけどねぇ」 パラソルの陰には、大きなクーラーボックス。中にはたくさんのジュースがギッチギチ。 しかも、ジュースはどれも高級品。 「……これまた、賞味期限寸前のデッドストック品だけどねー」 余計な予算を掛けずに夏を楽しむ。ただ、一つだけ違うのは……クーラーボックスの上に置いた、おニューの水着。 わざわざ本土から取り寄せた、特注品だったりするわけで。 ……こう見えても、えっちゃんも女のコですから? 「さぁ、思う存分バカンスを楽しむぞーっ! いっただっきまー……」 チェアに横たわり、ジュースの缶を開け、それを口元に近づける。 「ヴァイオラ、勝負だよっ!」 「また負けたいの? いい加減、学習したらどうかしら!」 ザザザッ! ズバァァッッ!! 突然、水着姿の少女たちが崖を駆け下りてきて、その勢いに巻き上げられた土埃がえっちゃん目がけて降り注いできた。 「うぇぇ、口がジャリジャリ……。一体なんなのさっ……」 「また、ヴァイオラちゃんと乱花ちゃんが勝負するんだって。今日は遠泳勝負だよ!」 乱花ちゃんを応援しに来たらしい倫花ちゃんも現れて、状況を説明してくれた。 いや、倫花ちゃんだけじゃない。二人の勝負を見に、一般クラスの生徒たちまでが続々と砂浜に現れた。 うずうず、うずうず。 ああ、なんだろ。休みの日なのに、商売人の血が騒いでる。 「うぉぉぉっ! 今日こそっ、ヴァイオラにっ、勝つっ!」 「威勢だけはいいようね。そこは褒めてあげるわ!」 砂浜を走り、二人は海に向かってダッシュする。 「二人とも、がんばって〜〜〜!」 黄色い声援が砂浜のあちこちから聞こえてくる。 応援している生徒は制服のまま、汗だくになりながら声を張り上げている。 ピィンと、えっちゃんの商売レーダーが儲け話の匂いに反応した。 「通信端末を持って来てて正解だった! 満腹丸ちゃん、アルバイトお願い! 倉庫にある水着の在庫とジュース、持てるだけ持って来て! あと、ビーチボールも! 超特急でよろしく!」 手早く商売の算段をつけ、そこで初めて一番の問題に気がついた。 「おーい、そこの二人-! そこ、浅瀬の向こうはサメがうようよいるから、遠泳はお薦めしないよー?」 すさまじい速度で、二人は砂浜に引き返してきた。 ◆ ◆ ◆ そこからは、えっちゃんの独壇場だった。 水着とジュースは売り切れ、ビーチボールも手元にある一個だけになった。 「……しまったなぁ。ビデオカメラも持って来てもらうんだった。せっかく着替え用パーティションも用意したのに、みんな砂浜で着替えるんだもんなぁ。眼福にも程があるよー」 水着を買った女のコたちの大半は、行列が出来ているパーティションを回避していた。 「ねぇ、越後屋ぁ。今日オフだって言ってなかった? もう夕方なのに、商売してていいの?」 「ちっちっち。愚問だよ、乱花ちゃん。えっちゃんは商売人だよ? 商機があるなら、魂以外ならなんでも売るさぁね!」 ……本当に、魂以外はみんな売った。 「ありがとね、越後屋さん。水着……助かっちゃった」 あのおニューの水着も、ついさっき、売れたところだった。 水着を買った少女は満面の笑顔を浮かべ、海辺で待つパートナーのところへと走っていた。 「マジであの水着まで売っちゃったんだ。わざわざ取り寄せたのに」 「だからさっき言ったでしょー? 魂以外は売るってさ」 「へー。商売人の鏡だね」 乱花ちゃんの言葉には、曖昧に笑って返した。 えっちゃんは、ヴァルキリーたちの笑顔のためにここにいる。 そんなえっちゃんが、水着がなくて困ってるヴァルキリーを放って置けるわけがないじゃん。 みんなに、笑っていて欲しい。 そしてお金が入れば、こっちもニッコリ。ほんの少し割増しで売れれば大爆笑や! 「でも、売るモノがなくなったら、商売人の時間は終わりだよね?」 乱花ちゃんが、売れ残っていた最後のビーチボールを手に取った。 「じゃ、遊びに行こっか」 乱花ちゃんが、そして遠くで手を振っている倫花ちゃんが、えっちゃんを見つめて笑ってる。ずっと遠くの沖で、ヴァイオラちゃんがサメと格闘しているのが見えた。 それからえっちゃんは、みんなで遊んで、笑って、たった数時間の休暇を存分に堪能したんだ。 そして明日から、また売って売って売りまくる毎日が始まる。 売った分だけ、みんなの笑顔が返ってくるんだよ。 だから商売ってのはやめられないのさ。